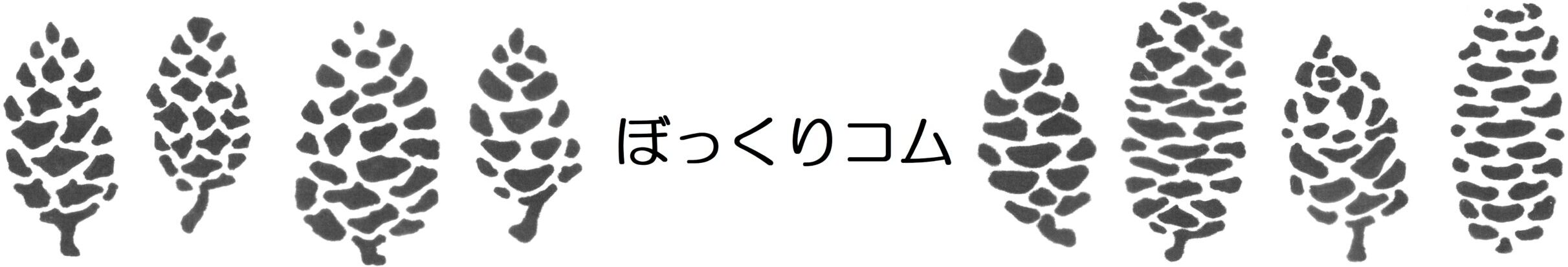なんやかんやで社会人生活3ヶ月、まあ想像したとおりの激務のなか、なんやかんやダッチョとのルームシェアも軌道に乗り、なんやかんや笑ったり泣いたりする日々を送っている。そう、ここではまだ書いてなかったけれども、文字通り、ダッチョと同じ釜のメシを食う生活をしているのである。
いきさつはこうだ。
俺たちはとにかく自立して実家を出たかった。というのも、互いにこの歳になって仕事もせず親のスネをかじらざるを得ない身分だったのだ。必然的にその実家ではなんとなく居場所がなくなる。メシくらい自分で稼いで食いたい、と猛烈に思うようになる。そしてお互い実家にいる間、猛烈にバイトをしながら生活資金を貯め、猛烈に就職活動をして就職し、その後しばらく抜け殻のようになった。
そしてやっぱり、実家を離れると何かしら自由を感じることができる。べつに何かに縛られてた訳ではないけれども、何も制約がないわけでもない。やっぱり常々、自分の行動を見られている目がある。それがなんだか面倒くさかった。
そして、そんなにネガティブな理由ばかりではない。なによりルームシェアは楽しそうだと思ったのが、動機としては一番大きい。実際かなり楽しんでいる。正直、あまり考えもせずに勢いだけで部屋を借りた。とりあえずそこは、我が城、というわけである。好きなだけ、勝手にして良いのだ。
俺は今まで夢に見ていた、クラブに置いてあるような巨大スピーカーを買って部屋に置いたし、ダッチョは初アパート自立生活とだけあって生活の様々なことを楽しんでいる。最初は家事も分担していたのだが、あまりに俺の仕事の帰りが遅いので、俺が家に帰ると家事のほとんどがすでに終わっている。就職当初、てっきり京都勤務だと思っていたのがなんと滋賀勤務を命ぜられたのだ。早とちりをして、もうすでに京都にアパートを借りてしまっている。毎晩終電で家に帰り、ときには終電に間に合わずタクシーを使った。家に帰るともうダッチョは何かしらメシを食い終えていて、俺はメシを食う元気もない。流しにあふれていた皿は見事に洗われて片付けられており、俺は申し訳ない顔をして、ただビールを飲みつつタコわさを喰らい、泥のように眠って朝を迎えるというサイクルだった。それを幸いダッチョは苦も言わず続けてくれた。
そんな生活もしばらく、俺は京都に転勤になった。滋賀での人間関係や仕事が軌道に乗りつつあったので戸惑いもしたが、よくよく考えてみればそれは妥当な条件の異動だった。カラダを休める時間も増えた。通勤電車に揺られていた時間が一日に3時間も余った。その時間を俺は、有効にダラダラと使って楽しんでいる。有効に。
ダッチョの生活はというと、驚くべきことにあれだけアウトドア嫌いだったはずが、今は中型二輪の免許をとって単独テント旅を計画しているのである。土臭い野営好きの俺が一歩も二歩も遅れをとってしまっていて悔しい。しかし俺だってこういつまでも黙って見ているわけがない。密かな計画がある。もちろん単独行である。俺たちは神島の旅から帰って、脳ミソはすっかり旅の人になってしまったのだ。もう取り返しがつかないし取り返すつもりもない。
ダッチョの休日は週末、俺の休日は平日なので一緒に旅はできない。それが逆に面白いではないか。旅先でどんな苦労があろうと素敵な出会いがあろうと(ほとんど無いけど…)、話を聞く上でしか共有できない。だがルームシェアをしている楽しみというのは、この、相手の話を聞くことに尽きるのである。お互いに同じ場面にいて同じ経験をすれば話をする必要などないのだ。お互い同じ釜のメシを食いながらも、全く違うライフスタイルを送っている。だからこそ、お互いの話が晩酌の最高の肴になるのである。
断っておくが、話の内容は極めてつまらない。しかし、それが良い。そこが良い。
そんな、とある日の出来事。
俺は仕事の帰りに自転車で必ずコンビニに寄る。もちろんその日のビールを買うためである。いつも通りコンビニの扉をくぐろうとしたとき背後から声がした。「ぼっくりくん?」。もちろん俺の名前なので振り返る。そこには、どうでもいい女が立っていた。数年前、友達の友達としてクラブで知り合った女だった。そいつはいつも自分の感情的な話しかしないので、面倒くさいという印象しかない女だった。
案の定、早くビールを買って家に帰りたい俺を食い止めてそいつは自分の話を始める。もうとっくに日付は明日になっていた。早く家に帰ってゴロゴロしたい。俺は猛烈にゴロゴロしたい。
話は1時間に及んだ。耐えられなくなって俺はその女を家に招いた。とにかくその女が居ようと居まいと、俺は一刻もはやくゴロゴロしたい。面倒くさい女がついてきたことには目をつぶろう、一刻も早くゴロゴロしよう。
これが間違いだった。それはその時点では気がつかなかった。
その女は、うちに着くなり彼氏と電話をし始めた。その彼氏というのは、俺の友達だった。
数分の電話なら良い。穏やかな電話なら良い。しかしそいつはとんだバカ女だった。家に招く前にそのことを忘れていた。
その女の電話は、電話が始まってものの数分で口喧嘩に変わった。俺とダッチョも、最初は放っておいた。しかし放っておくとその電話は1時間を経過した。時間が経つにつれ声のボルテージはどんどん上がってくる。俺とダッチョはいつもの貴重なゴロゴロ過ごす時間を、とにかく興味のない女のカナキリ声に支配され、ただただうなだれていた。それは、お互い泣くほど頑張って金を貯め、やっとの思いで借りたアパート、我が城に、初めて足を踏み入れた「女」だった。
俺はその女に言った。
「その電話まだ続きそうなら俺の部屋か外でやってくれる?やっぱ俺らも夜くらいはのんびりしたいし。」
女は言う。
「それって、ウチが迷惑モノみたいやん。」
その通りなのである。迷惑なのだ。わかってなかったのかよ。
時計はすでに午前2時を指し、ちょっと明日の仕事にも差し支えるからカンベン、と、こっちは穏便に言っているのだが。
その女はやっぱりクズだった。
「なんかぼっくりくんがさ、私らの会話をウザがってて迷惑そうにしてるから切るわ。ぼっくりくんって人間が小さいな。」
もちろん次の瞬間に出た言葉は、
「帰れ。今すぐ出ていけ。」
である。女は電話を切った。しかしその女はなかなか帰らない。自分の非は認めず、とにかく俺たちの批判をしてくる。もう、穏便に応対する理由など何もなかった。
俺は黙ってその女の荷物を玄関ドアの外に投げ捨てた。女が何か言っている。俺はもうすでにそれを人間の言葉だとは思っていない。排便時の轟きと同じような響きだな、と瞬間的に思った。
まだ女はなにか言いちらかしているだけで出ていかない。面倒くさいので力士のように張り手でそいつを玄関外に押し出し、すぐに鍵を閉めた。
驚くほど瞬間的に、普段の空気がまたそこに戻った。ゆっくりビールを飲み、ゆるい談笑と心地よい沈黙のなか、ただ何でもない今日のできごとを話し、また何も変わらない明日を迎える心の準備をそれぞれの中ですすめていった。それは全く、他人とはいえ驚くべき一致をみせる俺たち独特のペースなのだ。
ほどよく酔ったところで、それぞれの部屋に引っこんで眠りに就き、それぞれ定時に起きて仕事に行く。
そんな我が城にも、多くの来客があったりまた反対に誰も来ない日もある。
これからは、どうもそんな京都の片隅の、修学院というところに建つまあごく普通のアパートの一室を中心とした、なんとなく眠たげでアホで真面目な生活の記録をここに記していくことになるのだろうか。
まあ、さ。なんかえらく長期間のことを凝縮して書いたから、改めて読むと、何やら意味がわからん内容になっているな、ということは自覚しつつも、書き直すのが面倒くさいからモウイイヤ。
また気が向けば来週~。