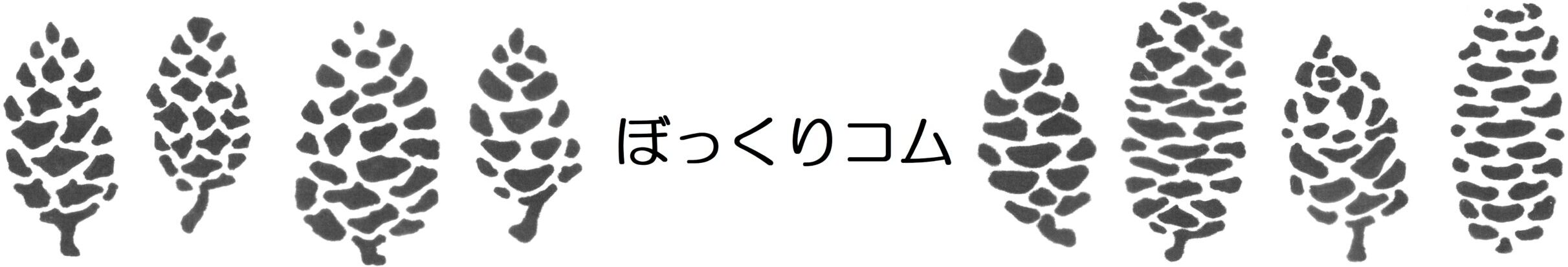研修で東京に来ている。今日はオフ日なのでホテルの自室にこもり、窓際にイスを置いてこれを書いている。ここ十日ほど本当に忙しく、体の芯がボーっとしてしまっている。
三月中旬の神島の旅から帰るとすぐさまバイトに復帰し、怒涛の労働地獄に突入した。昼夜問わず働き、寝ることもままならないバイト期間がすぎると間髪いれず東京へ出発し、目の回るほど忙しい研修期間をすごしている。
まず今までスーツというものをきちんと着たことがなかったので、朝の身支度にもいちいち時間がかかる。そして慣れない土地での電車通勤。常に集中力のいる研修が終わると毎晩のごとく酒宴となり、それが終わるとヘロヘロの頭をばりばり掻きながらその日の研修内容の復習…そして寝る間もわずかに朝をむかえる、というサイクルである。
東京に来るたびにいつも思うのだけれど、本当にここは金のかかる所だ。ちょっとメシを食うだけでもいちいち高いものばかりだし、安い店を探せばおもいっきり混んでいるし、電車は乗り継ぎだらけだ。
そして、せわしない。ゆっくり歩いている人なんてほとんど見かけないし、公園の陽だまりで昼寝をしている人や川原でたたずんでいる人も少ない。肩をぶつけられても謝るどころか睨まれるし、老人に席をゆずる人もいない。ここは俺の居場所ではないな、ということがだんだんわかってきた。
今日はせっかくのオフ日なので、どこか川原にでも行って本を読んでいようと思ったのだが雨が降るというので、あきらめてこれを書いている。のんびり書きはじめて一時間ほど経ったが、外はいよいよ雨が降ってきたようだ。少し窓をあけてみると駅前の喧騒が飛びこんできてやかましく、少しびっくりしてすぐ閉めてしまった。八階の部屋の窓からみえる空は灰色で重く、この街全体に満ちた憂鬱な空気に息がつまりそうだ。
連日のバイトで疲れていたことも理由のひとつなのだろうが、東京に出発した時からなにか心のなかに重く腫れぼったいものがつっかえているような気がしていた。この研修に来るまえの一ヶ月ほどろくに家族と会話も交わさず、アパートを借りるための資金作りのために必死で働いた。そんな期間が長くなってくると、家族の誰もが気をつかってか俺に話しかけなくなっていった。それもそのはずで、話しかけられても俺は返事すらしなくなっていたのだ。今思えばそれは毎日の疲れのせいというよりは、いよいよそこまで迫ってきている社会人生活への不安だったように思う。
そしてようやくバイト期間を終え、受け取ったのは三十万ほどの額だった。しかしそれはアパートの契約のために一瞬で消えていった。
部屋にこもって東京への出発準備を終え、あと数時間で家を出るというときに、ドアをノックする音がした。開けてみると親父が立っていた。まさか反応があるとは思っていなかったのか、すこし目を大きくして驚いているようであった。親父は少し間をおいて話しだした。
「スーツの用意はしっかりできてるか?」
「うん、ちゃんと揃えたから大丈夫。」
「そうか。いいスーツ買ったから要るか?」
「いいよ、ちゃんと足りてるから。」
こう言って、自分の声がここ一ヶ月ほどで染み付いてしまった鬱陶しそうな受け答えのトーンになってしまっていることに気がついた。それを聞いて親父は悲しそうに下を向いて、
「そうか。お前のためにせっかく仕立てたんだけどな。」
と言って黙ってしまった。俺は胸をぐっと締めつけられる感覚をおぼえながら、
「見せて。」
と言った。
それは本当に立派なスーツだった。親父は得意げに、それがイギリス製の高級生地でできていること、俺に気づかれないようにサイズを知るのが大変だったということ、仕立て屋の知人と何度も相談を重ねて作ったこと、上下で三十万もすることなどを、弾んだ声でおしえてくれた。
「三十万」という言葉が耳に残った。それが偶然にも、この一ヶ月で俺が稼いだ額と一致していて、その額を稼ぐ苦しさを身をもって体験した直後だったからだ。胸が裂けるほどにこみ上げてくる何かを感じながら、感謝のきもちをこめて「ありがとう」と言ったつもりだったのだが、口から出たのは鬱陶しそうな重いトーンの「ありがとう」だった。
東京に来て数日後、親父から電話があったが研修中で出られなかった。夕刻をむかえその日の研修が終わると、すぐ携帯電話を見た。留守電にメッセージが残っていたので聞いてみると、
「お父さんです、元気にやっていますか。とくに用事はありません。では。」
という親父のいつもよりおどおどした声が残っていた。親父が用事もなく電話をかけてくることなど今まで一度もなかったので驚いた。しかしその後すぐに同期全員のあつまる宴会があり、親父への電話は後回しになってしまい、そしてそのまま数日がすぎて今日になってしまった。
気がつけば窓の外はすっかり夜になっていた。雨はいっそう強くなっているようだ。ホテルの八階にある自室の窓辺にすわり、街を行き交う傘の群れをボーっと眺めていると、ある赤い傘に目がとまった。あざやかな赤だった。そしてふと、もしかするとこの街全体を満たしている憂鬱な空気というのは、まさに自分の心の内を映しているだけなのではないかと気がついた。そしてそれが呼び水になったかのように、もしかすると社会人生活へ不安を抱いていた俺の心を親父は察していたんじゃないか、ということに気付くと、俺は傍らに転がっている携帯電話を手にとった。