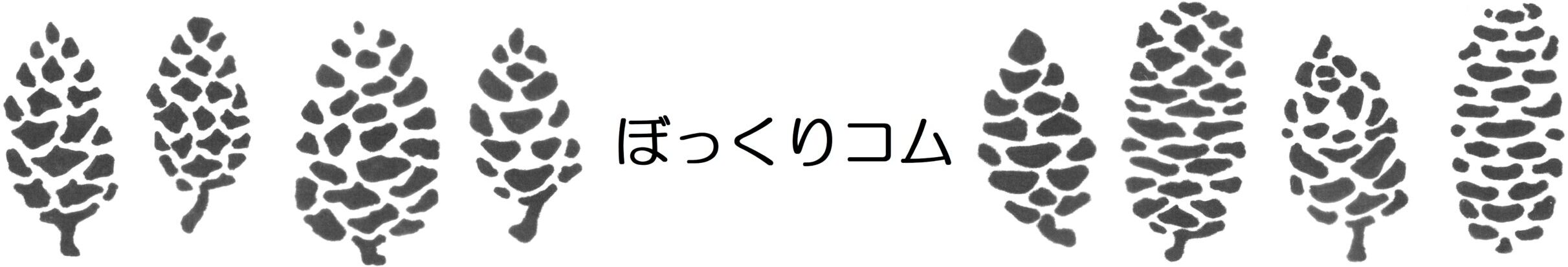名瀬の宿にもどったときには、あたりの街並みはすっかり夜の闇に包まれていた。8畳の部屋の窓をガラッと開けると、海からの湿って存在感のある風が顔に吹きつけた。冷え切った体の芯がぐったりと重い。冷たくはあるがしかしやはり南国の風の陽気なノリに、すっかり疲れも心地よく感じられるほどに心の底が開放されていた。
部屋にある電灯もテレビもつけずに、俺はラジオの音をなんとなく選んだ。旅先での、その地方地方のローカル局のラジオを静かに流しているのは心地いいものだ。海からのたっぷり重い風と、ラジオから低く低く聞こえる男性DJの声が、不思議な安堵と焦燥の入り混じる旅独特の感情を呼んでいた。好んで田舎の島に旅するおれはいつもこの感情を楽しんでいるように思う。もうとっくに自分の日常からは離れているのだけれど、しかしそこにはその土地のいつもと変わりない日常が流れている。そんな中で、自分の普段の日常からは遠く離れてしまっている状況が、もしかしたら予期せぬ事態でいつまでも続くんじゃないか、という、どこから湧いてくるのかよくわからない焦りと、もしそうなればそれもそれでいい、という開放的な気持ちとすべてを包んでくれそうな自然の大きさに、自分の中にざわざわと揺れるなにかを感じて楽しんでいるのだ。まさに、今のこの感情がそうだった。
それと同時に、こんな気持ちの時はキッパリと冷えたビールを飲むべきだ、と瞬間的に思った。
くたびれた民宿の、潮のくっついたネバっこい窓枠からすこし身を乗りだし、「酒」のたぐいのネオンを探した。するとそれはすぐ隣にあった。24時間営業ではないコンビニだ。いつ閉まるかわからないという急いた気持ちから、そこにすぐ向かった。
自動ドアをくぐると、オリオンビールのバリエーションがたくさんあることに驚いた。さすがここは南国なのである。迷った挙句、結局全種類買っていった。今泊まっている1泊2500円の安宿には、宿泊客共同の冷蔵庫があるので余ったらそこに放りこんでおけばいい。せっかくこんな特別な場所にいるのだ。飲みたいときに飲みたいものがない苦痛は大きい。全5種のオリオンビールを買い、すぐ隣の宿に戻った。
部屋に入るなりイッパツ目の缶をあける。これは奄美大島への挨拶の乾杯だな、と心の内で思いながら静かに一口。あいかわらず低く低く聞こえてくるFMローカル局の男性DJの声に心まどろみ、じっと口のなかで弾ける泡のひとつひとつを味わいながらとにかくまず南国をかみしめる。
しかしもうすぐ約束の時間だ。奄美出身、奄美在住の人と酒を交わす約束があるのだ。泡のプチプチもほどほどに鼻水のたれた服を着替えていると、電話が入った。宿からすぐの居酒屋で集合ということだった。
そこに向かうまでの所要時間は1分もなかった。もう窓から見えるほどの距離の居酒屋だったのである。島に来るまでにコンタクトをとっていた女性とその友人が、店の前で出迎えてくれた。連絡をとっていた「ひさの」さん、その友人の「あゆみ」さん。さっそく3人で中に入る。これが初対面だが、この一日で出会った島人とおなじく気さくな雰囲気を感じた。島だからであろうか。大阪の初対面の人と喋るのとは全く違う切り口である。オブラートに包んで包んで何が本当だか結局最後まで分からないような都会人の口ぶりは全くなく、すぐに素の言葉で話ができた。そこに奄美の郷土料理と酒が運ばれてくる。やはりサトウキビの島である奄美らしく黒糖で煮た豚の角煮が「島の代表です」と言わんばかりに存在感をもって姿を現し、アカウルメの塩焼きや油ソーメンが続く。ぎっとりとしたイメージの湧くメニューであるが、実際に食ってみるとそれは意外にもサッパリとしていて、そこにやはりこの地域に深く伝統をはらみながらずっと残ってきた大衆食であるということを実感する。決して京都の八橋のようなハリボテ的存在ではないのだ。
そうして奄美の郷土料理を口に運びながら、歯に衣を着せない話はすすむ。気持ちいいくらいにトウトウと飲んでくれる女性二人の話はとてもローカルで面白く、ずっと時間をかけて聞いていたかったのだが、この居酒屋のラストオーダーの時間は突然に、遠慮がちに大将からそっと告げられた。
気分の良いまま店を出ると、やはり海からの風が気持ちいい。ここから海まではわずか300メートルくらいしか離れていないのだ。生々しい海風がフワフワと体をなでていく。
そうして風を楽しんでいると、女性2人の友人が偶然にも同じような境遇で向かいの居酒屋から出てきたようで、自然に「合流」という運びになった。
そのまますぐ近くのライブバー「アシビ」に流れ着いた。どかっと大きなテーブルを囲んで思い思いの酒を注文する。しかしそこで気がついた。どこかで聞いたことのある声がすぐ近くから聞こえる…。それは俺の向かいに座っている男前ニイチャンの発する声であった。
すぐ分かった。それはさっき聞いていたFMローカル局の、低く低くおちついたトークを繰り広げていたDJの声そのままだった。そのニイチャンはその声の本人だったのである。
そのニイチャンの名前は「タイシ」といった。となりに座っているオジチャンがそう呼ぶから分かったのだ。そしてなんと面白いことに、その「タイシ」ニイチャンはやはり局でDJをしており、その隣のオジチャン「フモト」さんはそのFM局の代表取締役なのであった。なんとも偶然にも気持ちのよい成り行きで、そんな会心の出会いを果たしてしまったのである。そしてやはり話は弾む。
俺は初対面だが、ひさのさんやあゆみさんは幼少からの旧知の仲だそうで、地元の言葉で会話が弾んでいる。俺もなんとか喰らいついてその話を聞いてみたい一心で切り込んでいく。奄美の言葉は話せないけど、島の言葉でいろんな話を聞くことができた。
今でこそ奄美大島といえば観光地のひとつとして数えられるようになったが、以前はそういうこともなく若者が島から出ていく一方だったこと、島の仕事はやはり少なくて苦労していること、伝統文化が色濃く残るこの島にはユタやノロといわれる易者がいること、易者だけではなくこの島にはニライカナイの思想に通ずる自然神の信仰が根強くあり、それによって奄美の大自然は残されてきているいこと、元ちとせの実家の水道の蛇口からはエビが出てくるということ、ここにいるみんな一度都会には出たがやっぱり奄美大島が好きで島に戻ってきたその経緯など、それはそれは刺激的でたまらない夜の島人の「歯に衣着せない」そのまんまぶっちゃけ話の連続であった。
酔いきった朝方、惜しみながらも宴はおひらきとなったが、あゆみさんが翌日仕事が休みなので車で奄美を案内してくれるという。ありがたいことだとその話に乗り、宿の玄関まで送ってくれた皆と別れた。
部屋にもどると窓は開けっ放しで、ラジオもつけっぱなしだった。ラジオからは奄美の民謡が静かに流れていて、フワッと部屋に舞いこんできた風もやさしく俺をこの島に迎え入れてくれているようだった。民謡の合間に聞き覚えのあるやさしく低いDJの声がきこえた。タイシさんだ。それを聞きながら先ほどまでの愉快な話たちを思い出し、内側から愉快に軽くなっていく自分の心を感じつつ、布団に身をもぐらせた。
窓を閉め忘れたせいでいくらか潮の匂いのついてしまった布団のやわらかさが、まるでここがずっと住み慣れた場所であるかのように優しく感じられて、すっと寝入ってしまったのである。