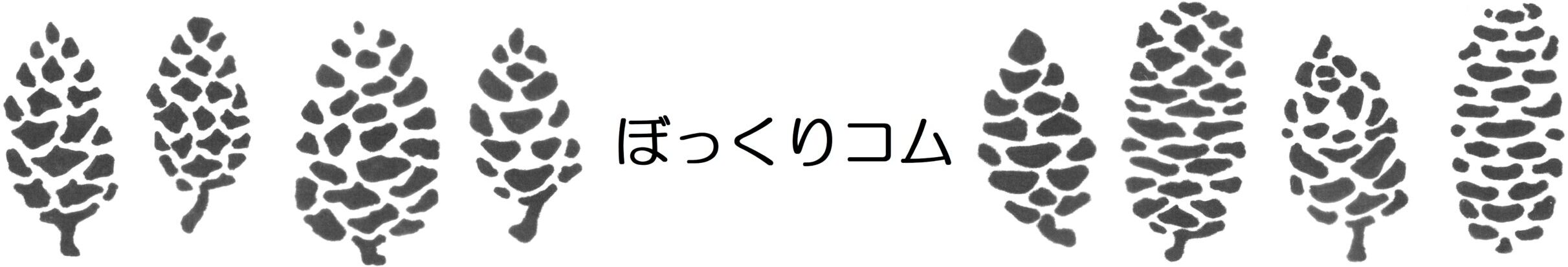元旦翌日の夕方から「よれよれ野営会」と題した焚火酒宴をした。これもまた瓢箪崩山という近所の山である。岩倉というところは本当に四方を山に囲まれたところなのだ。なかでもこの瓢箪崩山がいちばんのお気に入りで、よく夏場など一人でやってきては小川の冷たい水に足をひたし、岩のうえに寝ころがって読書などしていた。山だからもちろんあたり一面が木陰なので涼しく、夏のむし暑さも忘れさせてくれるお気に入りスポットなのだ。
しかしそれも一月になると涼しいなんて悠長に言ってられるようなものではなく、当たり前だけど猛烈に寒い。だから「よれよれ野営会」では防寒のためにえらく大がかりな準備をしなければならなかった。いくら気分はよれよれでも、寒さでよれよれになるのはご免である。
ちなみにその日の京都市の予想最低気温はマイナス1℃だったので、京都市の北はずれの山間部の川沿いのそこはさらに3℃ほど低いマイナス4℃といったところだろうか。焚火はあるのだが、念のため灯油ストーブに5人用テント、シュラフ等も準備した。
これを計画したのは俺とダッチョである。気がつけばダッチョとはクリスマス前後から毎日いっしょに遊んでいるのだ。なんだかキモチがわるいなぁ。
いつも仕事で忙しいボーボも今日は正月休みだというので、軽ワゴンで大荷物を山に運んでもらった。秘密のスポットに着いてさっそく準備を開始する。ダッチョは焚火をおこし、ボーボは車から荷物をおろし、俺は景気づけにCDラジカセで音楽を流そうかと思ったら家に肝心のCDをそっくり忘れてきたようで、チャリで取りに帰る。
CDを取りに帰ったついでにトモちゃんをつれて山に戻ると、もうあらかた準備はすんでいた。トモちゃんがカラ付き生ガキの差し入れを持ってきたので、それを見た皆の眼から炎がボウッと吹き出たのを俺は見逃さなかったぞ。そして静かに視線でおたがいを牽制し合い、少しうわずった気持ちを落ちつけると皆に缶ビールが配られた。よおしよおしブシッと栓をあけ、皆で乾杯。宴の始まりである。
焚火と灯油ストーブのダブルアタックでほこほこと暖かく、いいねぇいいねぇと優しい気持ちになってビールをぐいと煽る。ぱちぱちとはぜる焚火を囲んでしばしほっこりとし、上空の木々の隙間からわずかに見える星空をしずかに眺めたりした。これが夏の焚火ならば話は大きく違ってくる。「おらおらおらぁビールビール!」と血眼の怒号がとび、網で肉を焼く目もなぜか血走り、その脇では川の流れに逆らって必死にクロールする奴がいたり、活気ミナギルといえば聞こえはいいのだが、なんだかせわしないなぁという気持ちも否めない。またそれもイイのだが、冬くらいはこうやってほっこりと静かに焚火を囲むのもまたイイものだ。
しばらくしてボーボとトモちゃんがマアミちゃんを迎えにいった。マアミちゃんはトモちゃんの仕事の一歳下の同僚で、俺たちと同級生のウエノのいとこにあたる。ウエノは文学少女っぽく真面目なイメージだったが、いとこのマアミちゃんはダンスをやっていて元気で垢抜けている。ここで5人あらためて乾杯。
そろそろ肉でも焼くかぁ!と思ったら焼き網を忘れていた。これだけ大荷物でやってきたのに肝心なものをいろいろ忘れてきてしまっているのだ。しぶしぶダッチョが俺のチャリで家に取りにかえる。
しかし非情にもここでカキが焚火に投入されたのだった。
カキがふつふつと香ばしい湯気をたてはじめた頃、猛スピードでダッチョが帰ってきた。「間に合いやがった」というテロップが皆の頭上を通過していく。しかしさすが元アウトドアショップ勤務のダッチョ、持ってくるのは焼き網だけでいいのに本格バーベキューグリル「スノーピーク ツインバーベキューボックス プロ」を持ってきた。なんと堂々と「プロ」と命名されたシロモノである。俺のよれよれテント(ホームセンターコーナン製3000円)とはえらい格差である。しかしダッチョは根っからのインドアよたれ男なのでこんな本格セットはきっと持て余してるにちがいない、いつか強奪してやらねばなるまい。
しかしそんな邪悪な考えもほくほくに焼けたカキの旨さでふっとばされた。あまりのウマさに俺はしばし唸り、ボーボは夜空に吼え、ダッチョは黙々と食らいつき、トモちゃんとマアミちゃんは奇声を発した。
その後ようやくダッチョの本格グリルが活躍をはじめた。肉やソーセージが焼き上がるたびに吼えたり唸ったり黙ったり、しばしせわしない状況がつづく。つめたい川で冷やしたビールが、焚火でチリチリと火照ったノドに果てしなくウマイ。CDラジカセからゆるーい音響系音楽や民族音楽がたえず流れていて、ああもうマイッタマイッタと言いつつぐんぐん飲み進む。
ときどき小便がてら焚火を離れ、ついでに倒木を拾ってきては薪にした。焚火を離れると山のつめたい空気が火照った顔にきもちいい。腹がすこし落ち着いてくるとそんな余裕がでてきて、倒木をひろう手をふと休めては遠くの焚火に照らされる皆を眺めてみたりした。
俺はこの瞬間がけっこう好きなのだ。わいわい人が集まっている場をすこし離れ、それを遠くから眺めてみるとなんだか胸のあたりがザワつき、涙がこみあげてくるような感覚に襲われる。この感覚には小学生の頃、少年サッカーの練習中に気付いた。
少年サッカーチームの練習は学校の授業が終わってから始まるので冬場になると日が暮れてしまうことが多く、日没後はナイター照明を使っていた。しかしナイター設備といっても小学校のグランドの規模なので隅々まで明るくはならず、ボールがグランドの隅に転がっていくと暗い中を探さなければならなかった。
隅までボールをひろいに行ってさあ戻ろう、と顔をあげてグランドの中央を眺めると、ボーっと薄暗いオレンジ色に照らされた仲間が動きまわっていてコーチが叫び声をあげている。もしここで俺が死んでしまって幽霊になったら、もうあそこには戻れないんだな、死んだ人の気分ってこんな感じなんだろうな、と思ってしばらく暗いグランドの隅で呆然と仲間たちを眺め、その度に胸をザワつかせ涙のこみあげるような感覚を感じていた。
今もそうやってその感覚を楽しんでいるのだが、あんまりそんなことばっかりしてると変なやつだと思われるからなぁ。そそくさと皆のもとに戻る。
焚火に戻るとだいぶ穏やかな雰囲気になっていた。また少しビールを煽り、ぼんやり炎を見ているとトモちゃんが「だれか来た!」と叫んだ。暗い山道に懐中電灯の明かりが見える。書き忘れたが、この「よれよれ野営会」は基本的に現地集合なのである。トモちゃんとマアミちゃんは特例というわけだ。だれが来たんだろう、という気持ち半分、もしかしたら麓の民家から苦情がきたのかもしれないな、と思って俺は道まで出てみた。
明かりはだんだんと近づき、暗闇からやっと顔を覗かせたのは、同級生の女の子イケノだった。
また皆のボルテージが上がり、その後しばらくトーンの高い会話が続く。しかし来る奴来る奴みんな差し入れを持ってきてくれるので、みんな大人になったんだなぁと思った。トモちゃんはカキ、マアミちゃんはワイン、イケノはカラアゲという具合である。さっそくカラアゲを直火で温めて食った。マアミちゃん持参のワインはワインオープナーがなかったので泣く泣く持ち越しとなった。残念。
ひととおり食うものを食ったので落ちついてテーマどおりよれよれの会話が続いていたのだが、トモちゃんとマアミちゃんが翌日の仕事のために帰宅となった。残った4人でもまたよれよれ話を続けていくと、気がつけばもう深夜の3時をまわっていた。あとでわかったのだが、ちょうどこの頃ショウゴがこっちに向かっていたのだそうだ。しかし場所を勘違いして山の麓あたりをうろつき、誰もいないので帰ったのだという。こっちは山奥なので携帯電話の電波も入らないし、すっかり宴は終焉したと思ったらしい。小泉総理風に言えば「まことに遺憾である」。
ショウゴは酒を飲むとリトマス試験紙のように瞬時に顔を赤く染め、テンションがうなぎのぼりに上がっていく奴なのでこういう場にはもってこいなのだ。自慢の腹を出して踊ってほしかったなぁ。
さあ朝も近くなっていよいよ眠くなってきた。しばらくしてイケノも帰宅し、ボーボもそのまま仕事に向かった。ボーボはこの魅惑の酒宴のなか、よくシラフで耐えたよなぁ。そしてやっぱり残ってしまうのは俺とダッチョなのだ。ボーボが帰ってしまい車がなくなったので、俺たち2人は残された大荷物を前にただただ呆然とし、よれよれとその場にヘタリこむと、黙って焚火に薪をくべ続けていくのだった。