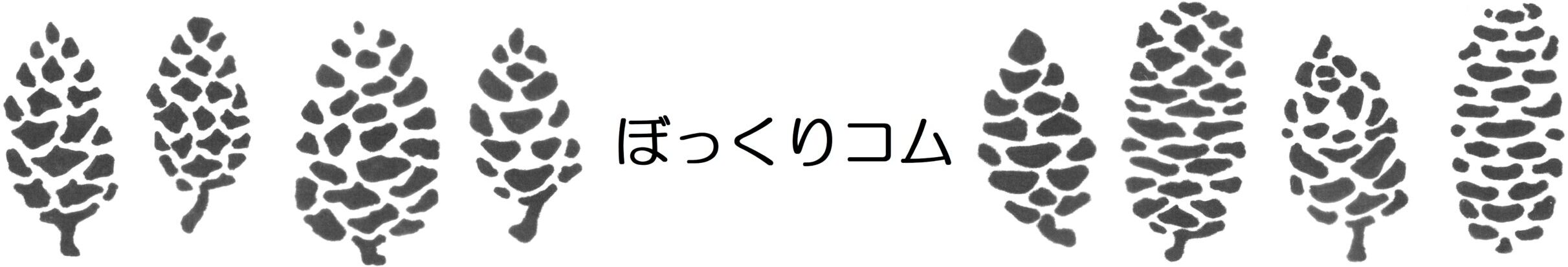神島に行ってきたぞ。三重県鳥羽市沖14キロに浮かぶ潮騒の島、神島。メンバーは先週書いたとおり、俺とダッチョとボーボの三人である。
俺は小学六年の頃ある本で神島を知ってからずっと神島行きを夢見ていたので、船の窓から島の姿を見たときは涙が出そうだった。そんなバクハツしそうな興奮を知ってか知らずか、島の船着場で俺たちを出迎えてくれたのは強い海風と灰色の重い雨雲であった。昼前のがらんとした漁港に、タコ壷がたくさん積まれていた。
テント泊の荷物をのせたキャリーカートを引きながら三人で歩いていると、すれ違う人がみな声をかけてくれた。島のひとびとは温かかった。坂道をおりてくる小学生も、よもぎ採りをしているおばさんも、漁港で作業をしているおじいさんも、道ばたで立ちつくしている犬も、みんな気分よく俺たち三人を相手してくれた。
雲行きが怪しかったので、古里の浜というところにすばやくテントを張る。そして水道水をもらおうと、ポリタンクをもってすぐ近くの神島中学校に入り、まず職員室に顔を出した。
職員室には四人の先生がいた。俺たちが浜でテント泊することを知ると、「今晩は嵐になるよ、この島の嵐はすさまじいから十分気をつけてね」と注意をくれた。雨が降るということは知っていたが、嵐になるというのはまったく知らなかった。
水道水を汲ませてもらっている間、鳥羽から海底パイプで引いているこの水道がなかったころの神島の水事情を教えてもらったのだが、周囲4キロほどの小さな島なので真水はかなり貴重なものだったそうだ。満タンになった10リットルのポリタンクを眺めて、しみじみありがたい気持ちになった。
古里の浜にもどると、風がさっきよりだいぶ強くなっていた。教えてもらった通り、いよいよ嵐が近づいているようだ。もしかしたら高波をかぶってテントごと流されるかもしれないと思って、三人分の三張りのテントをもう少し浜の奥まった小高いところに移動させた。
職員室での注意とこの移動が、その後まさに命を救ったと言っても過言ではないぞ。もう本当にこの島の嵐はすごかったのだ。

移動しおわって、それぞれ一人用のテントの中で荷解きをしていると、ドッ!というかんじで雨が降ってきた。それと同時にとてつもない風が俺たちのテント村をおそい、それは時間の経過とともにどんどん強くなっていった。まるで台風直撃の室戸岬、といった様相である。
水をもらったポリタンクをテントから5メートルほど離れたところに置いていたのだが、雨と風が強すぎてそこまでたどり着けない。それでも無理してテントから出ようとすると、自分の体重で押さえていたテントが飛んでいきそうになる。テントを地面に打ちつけておくペグは通常の20センチのものでは簡単にぬけてしまって全く役にたたず、70センチほどの流木をペグがわりに地面深く打ちこんだのだが、それすら暴風にひっこ抜かれてしまう。ダッチョはテントごと何度も空中に浮いては「オガーヂャーン!」と叫んでいるし、ボーボはもう数時間ものあいだ悲鳴しか発していない。5~6メートルもの高波はすさまじい轟音とともにテトラに打ちつけ、そのしぶきが30メートル離れたテントにまで飛んでくる。そうこうしているうちに、もう夕刻になっていた。
俺はその間なにをしていたかというと、ひたすら尿意に耐えていた。小便をしたくても、外に出たらアッというまにテントは飛ばされて、家なき子になってしまう。しかし膀胱の限界はもうそこまで迫っている。けど家なき子はイヤだし、だからといって24歳にしてオモラシはもっとイヤダ…。
そんな葛藤のなかテントの天井を見上げて風と雨のおとを聴いていると、雨粒の音がふと止んだ。しめた!と思ってテントのジッパーを下ろし外の様子をうかがってみると、風もちょっと一休憩、という感じで弱まっている。今しかない!そう思ってテントからとび出した。
コンチクショウ!という気分で海にむかって立小便をしてやった。が、もちろん高波が怖いので波打ち際からは数十メートルも離れていたが…。そんなへっぴり腰の俺のこころを見透かしてか、まるで天罰のようにいきなりドサッと大粒の雨がふってきて、ずぶ濡れになった俺は「これじゃあもう小便を漏らしたのと何も変わらないじゃないか…」と落胆してテントにもどった。家なき子にならないように、駆け足で。
自分のテントにもぐりこんでふと気付いたのだが、こんなに近くにいるのにもう数時間もダッチョとボーボの顔を見ていない。みなそれぞれ個人のテントにこもって、ぴっちりと入り口のジッパーを閉めているのだ。その中ではきっと小動物のようにコキザミに震えているはずである。
びしょびしょになってすっかり開き直った俺はなんだか大地の神様のような気分になり、テントのなかで湯をわかし非常食のマカロニを大量に茹でて、各テントに配ってやった。しかしダッチョもボーボも、テントの細くあけたジッパーからひょろりと片手だけ出しマカロニの入った皿を受けとると、すばやくジッパーをしめた。あいかわらず強い風と激しい雨と、波がくだける轟音があたりに響いている。大地の神様というよりは、戦争中の食糧配給のオジサンのような気分になって自分のテントにもどった。

また各自テントのなかで震えていると、波の音があまりにも大きくなってきているのが気になり、ジッパーを少しあけて外を見てみた。すると何てことだ、潮が満ちはじめていたのだ。浜を守っているテトラを越えんばかりの高波が、満潮にむけてさらにその高さを増してきていたのである。それには三人ほぼ同時に気付いたようだった。いつ波がテントまで到達するかわからない。
「どうする!?」「だれか満潮時刻を調べろ!」「午後7時!」「しかも大潮」「…どうする?」
ここでようやく会話らしい会話が交わされた。しかし暴風のなかで声はうまく聞きとれず、いまいち意思の疎通ができない。けっきょく会話は途切れとぎれでうまく成りたたず、もう少しこのまま様子を見よう、という空気がテント村に流れた。
満潮時刻まであと2時間。ここからは、ひたすらに恐怖と絶叫にまみれた夜を過ごしたのであった。なんというか…絶叫しすぎてもう細かいことは覚えていないのである。
嵐の夜から一夜あけて、早朝にへろへろとテントから這い出してみたら、まだ二人はそれぞれのテントで寝ているようだった。ポリタンクの水で口をゆすぎ、空を見上げてみた。雨はあがり雲も切れたが風はあいかわらず強く、波もテトラに打ちつけてはドゴォーンと腹にひびくような轟音をたてている。そうしてただ波が砕けるのを眺めていたら、空がぼんやり明るくなってきていることに気付き、とりあえず日の出をおがみに島の東のほうに歩いて行ってみることにした。
テントを張った島の西にある古里ノ浜というところから、ちょうど南回りで島を半周することになる。もうだいぶ明るくなってきているので、日の出に間にあうように急ぎ足だ。体が飛ばされそうな強風のなか海沿いの細道をずんずん進むと、ちょうど島の南端にある神島中学校あたりからは上り坂になっていた。さらに進むと細道は階段になっていて高度をさらに増し、その横はガケになっている。身をのりだしてガケ下をのぞいてみると、50メートルくらいの切り立った岩のガケ下で白波が砕けていた。

ここで突風がふけば間違いなく落ちて死ぬなぁ、と思うとゾクッとして体の力がぬけた。そして腰を抜かすようにヘナッと腹這いになって岩にしがみつきガクガクしていると、次の瞬間、目の前の海がカッと明るくなりドーンと日が昇ってきた。おれはガケの上で腹這いになりながら、無残な姿で日の出を拝んだのである。

まあいつまでも岩にしがみついていたって仕方ないので、ずりずりと這って階段道にもどった。日は完全に昇ってしまったので当初の目的はなくなったが、昨日の嵐のせいで神島探検がまだできていなかったのだ。そしてそのまま階段道をすすんでみることにした。
数分ほど歩いていくとやっと平坦な道になった。そして目の前にコンクリートでできた古い建物が現れた。観的哨(かんてきしょう)だ。

観的哨というのは戦時中につくられたコンクリート製の小屋で、伊良子岬から撃った大砲がどこに着弾したかを確認するための物見やぐらのような役目をはたしていた。そして役目を終えた今もそのままそこに残っているのである。
と、あたかも事前に知っていたかのように書いているが、その観的哨の横に立っている看板にそう書いてあったのだ。フムフム、と思いながらその小さな建物に侵入。扉などは完全に朽ち果ててなくなっており、コンクリート部分だけが残っている。階段をのぼると2階もさほど1階とかわらない簡単な造りになっており、そのままさらに階段をのぼって屋上部分に出た。

すると、なんとまぁ…パノラマの伊良子水道が目の前に広がり、昇った太陽がぎらぎらと海面から照りかえしているではないか。ここから日の出を見れたとしたら、きっと泣けたに違いないなーと思うと妙にくやしくなってとりあえず叫んでみた。霞みのかかった伊良子水道はそんな声には目もくれず、ただドバーン、ドバーンと眼下のガケを打ち続けていた。
テント村に帰ると、ボーボがのそのそと起きだしてきた。二人してボケーっと海をながめ、とりあえず意味もないため息をついてみる。白い三角の波頭のはるかむこうに、鳥羽の街が揺れていた。あまりの嵐の激しさにほとんど寝ていなかったのだが、島の朝は早い。もう島の人々は起きてなんやかんやと活動を始めているはずなのだ。島の全貌をとりあえず把握しておかねばならぬ、島の人々の生活なるものを目撃し、にわか島人になる必要がある!と、まだテントで寝息をたてているダッチョを置き去りにして、俺とボーボは島探索をはじめた。
とりあえず歩き出してみると、気付かぬうちに、さきほど通った観的哨(かんてきしょう)への道のりを歩いていた。神島小学校のわきを通り、断崖のへりの道を歩き、急な坂道をのぼりきると観的哨が現れた。観的哨を目の前に、ボーボはしきりに感動し「うーん」と唸りながら難しい顔をしている。こいつはどこでもここでも、とりあえず難しい顔をしながら難しい言葉を発することを生き甲斐としている男なので、面倒くさいので俺はそんな顔をしはじめたボーボには気付かないフリをして、観的哨の階段をのぼっていった。

日が昇りきった景色も圧巻であった。伊良子水道の轟音を聞きながら二人して黙りこんで、とりあえずカバンから焼酎をとりだしシェラカップに注いだ。黙ったまま海を眺め、焼酎をぐびっとやる。うーん。難しい顔の奴とは反対に、俺は全身の筋肉を緩めきってシアワセな奴へと変化していく。なーんも文句ない文句ない。とりあえずシアワセであった。
とくに俺たち三人はコレといった目的もなくこの島にやってきて、とりあえず酒だけ切らさなければあとは何だっていいよ、という、なんか「現代の若者」というよりは「飲んだくれオジジの行く末」というべきか、まあ、あまりキリッとしていないことだけははっきりしている三人の旅もようやく、よっこらしょうと午後へ向かっていった。

観的哨からは下り坂になっていった。島を反時計回りに歩いており、ここはちょうど3時くらいの位置である。どんどん高度を下げ、12時の位置にある集落へと向かっていた。10分も歩くと建物が増えはじめ、いよいよ集落へと入っていく。くねくね入り組んだ民家のすきま道を抜け、漁協のある中心地へ出た。

人影はチラホラとしか見えず、がらんとした港に風が転がっていた。まだ海は波が高いので漁に出ることができなかったのだろうか、賑わっているはずの午前中の漁港は拍子抜けするくらい何もなかった。たばこ屋のブリキ看板が揺れ、よろず雑貨屋のガラス戸がガタガタと音をたてている。細道からひょっこり顔を出したオバチャンに声をかけてみると、やはり今日はほとんどの漁師が休漁しているのだという。この高波では、堤防でゆっくり釣りをすることもできないし、漁協でいろんな魚介類を手に入れることもできなかったし、それならテント村をつくった浜でごろごろと一日を過ごそう、ということになって、よろず雑貨屋のガラス戸を引きビールをたんまり買ってテントのある浜へと戻った。
浜に帰ると、ダッチョはまだ寝ていた。
浜ではただひたすらゆっくりな時間が流れていた。買ってきた缶ビールを、まだ冷えてるうちにプシッと開け、海を眺めながらボーボと乾杯をする。目の前の海では、前日までの嵐の影響をたっぷり残した海が、豪快な波頭を躍らせている。そうして気分よく飲んでいたのだが、なんだか手持ち無沙汰な気分だった。こんなに文句のない景色と酒まであって、何が不満なんだ?なんだなんだ?と足りないものを頭に並べてみる。睡眠時間、金、彼女、地位、名誉、おさかなさん、貝たち…あ、そっか!酒のつまみがないのだ。前半の重い欲求はとりあえず記憶の底のほうにしまっておいて、俺はボーボのほうを向き、厳しい顔をして「貝、獲るぞ」と告げた。

この波の高さでは魚釣りは無理だから、貝ならなんとかいける、と考えたのである。そんな甘い考えだから、目の前の波頭踊る海に今まさに入らんとす!波と闘う俺!!という男らしい勇ましい心づもりではなく、まあさ、ちょっと酒のアテに貝とかあったらいいよね、無いよりはあったほうがいいよね、ねっ☆といった、若干うねうねとした軟弱な考えであり、厳しい顔をしてみたのは照れ隠しのようなものだった。ボーボはぶっきらぼうに「おう」と一言だけ答え、そのわりには軽やかな足どりで俺に続いた。持ち物はビニール袋だけという軽装である。そして俺たちは目の前の荒波はじける岩場の、そのはじっこの波のあんまり来ないテトラに向かった。

体の小さい俺がテトラの隙間に入り、見たことないけどとりあえずデカイし食えそうな貝を獲る。そして得意気に「ほら、これがトコブシっていう貝でな、塩茹でするとウマイねん」と、あたかも知っていたかのようにボーボに説明する。そしてボーボも「ほぉ」と言って関心しながら俺が獲ったそれを手にとり、しげしげと見つめてからビニール袋に放りこむ。あとで知ったのだが、それはマツバ貝というもので、偶然ながらも「塩茹でするとウマイ」とのことだった。まあ海のマイナーな貝はとりあえず塩茹でしてみるとウマイというものが多い。そりゃ四六時中海の塩にさらされてるわけだし、もともと塩味なのだから逆らわないでおこう、という考えもあながち間違いではないようだ。
まあしかしそこにいる俺はそんなことはまだ知らないわけで、ほんとに食えるのか少々ドキドキしながらボーボの表情をうかがいつつ、ウマイ貝だと信じちゃってるんだから俺のこのドキドキは墓場までもっていこう!とか心に決めつつ、しかしここに書いてしまってるわけですな。願わくば、ボーボはこれを読むな!
そして小一時間トコブシ(ほんとはマツバ貝)を獲って、ある程度ビニール袋がいっぱいになったのでテントのあたりに戻り、小さなシングルコンロでそいつを塩茹でにしてみた。てっとり早く海水で茹でているだけなのだが、なかなかウマそうな匂いが漂ってきたではないか。意外にもウマイかもしれない…傍らではボーボがすこしメルヘンなほど目をキラキラさせて茹であがる貝たちを見つめているので、ウマくないことなどあってはならないのだ。おれには子供の夢を踏みにじることなどできない!!
さて茹であがったそいつを、酒のアテに向くようにさらにショウユ漬けにする。ここまでくると、ちょっと「ウマイかもしれない」という安堵が俺にも漂いはじめ、おだやかな気持ちになってビールをあおりつつ貝がショウユにひたっているのを眺めていた。そして実食となったわけだが、俺の心配をふっとばすほど、その貝は文句なしにウマかった。そして俺はまた得意気に「ほら、ウマイやろ」とボーボに言ってみせたのである。
そんなウマそうな匂いを嗅ぎつけてか、ダッチョが目をさましテントから這い出してきた。メンバー1の食いしん坊だけあって、「俺にもくれ」などと言うのだろうと身構えたのだが、ダッチョは開口一番、
「うんこしたい」
と小さな声で言った。
そういえば昨日の嵐でテントから離れられず、野グソひとつできていなかったのだ。テントを一歩でも離れようものなら、それまでなんとか体重で押さえていたテントは軽々と空に浮かび、そのまんま暴風のかなたへ飛んでいってしまうくらいの嵐だったのである。かくして俺達は大腸のあたりにしっかりとうんこを蓄えていたのだ。そのことを俺とボーボも同時に思い出さされてしまい、3人そろって便意の人となってしまった。そわそわと辺りを見回してみると、野グソに最適な茂みなど腐るほどあった。しかしそれじゃあ芸がない、と、3人同時に思ったのだろう。ボーボは静かにそびえ立つ崖のてっぺんを指差し、「俺、あそこでする。ひり落とす!」ときっぱりと言い切り、決してそんな姿など見たくない俺とダッチョは「じゃあ俺たちはもうちょっと離れたとこで…」と言い去り、ボーボを残して茂みのほうへ。影が小さくなっていくボーボを背中に感じつつ、しかし便意にも焦りつつテントから遠ざかっていく。すこし歩くと、公衆便所とは言えないまでも、茂みのなかに朽ち果てたコンクリート製の汲み上げ式の便所らしきものがあった。もう何十年とだれも使っていないのだろう、今にも崩れそうな便所である。しかしもう悠長に便所の外観を眺めていられるほどの余裕はなく、肛門をノックしているうんこさんに背中を押されるようにその便所へ二人して駆けこんだ。
大便用の個室(?)がちょうど2つあり、べつに便意に焦ってないような表情をしながら焦ってそれぞれの個室に入った。個室とは言ってもドアはとっくに朽ち果ててなくなっており、浜からの風がさわやかにケツをなでていく。しかしこれが島のクソの醍醐味である。俺は先陣を切ってその便所の穴に特攻隊をひり落とした。もう完全に干上がった便所の穴の底にどすどすと攻めていく俺のそいつらを穴の上から眺めつつ、さわやかな快感に全身をつつまれていると、どうやらダッチョも同様な様子で、快感の吐息をもらしていた。
そしてふと気になり、ドアのない個室から遠くのテントの方向に目を向けみると、テントの横にそびえ立つ崖の中ほどに、点のように小さくなったボーボが張りついているのが見えた。あいつはまだ崖のてっぺんをめざしながら便意に耐えているのだな、と、どこか優越感を感じつつ俺は脱糞を続けた。そしてまたもう一つの個室から、ダッチョの快感の吐息が響いていた。
脱糞しおえた俺たちにはまた退屈な時間が待ちかまえていた。これが真夏の浜ならまだしも、まだ冬の気配の残る3月であり、しかも目の前の海は大シケときている。しかし何もすることがないというのは幸せなことなのだ。酒があり、寝床もあり、大シケの海も眺めている分には楽しい。
しかし島でのテント生活というものは、のんびりしているようで実はそうではない。一日三食の食事の準備に終始するというのが普通である。たとえば家庭なら米は炊飯器が炊いてくれるし、料理するにもキッチンがあってコンロがあってフライパンがある。しかし俺たちのテント旅は「軽装」が基本なので(というより電車移動なので軽装にせざるをえない)オートキャンプや青少年キャンプ村ヤッホーヤッホーといった便利旅ではなく、基本的にはほとんどのものを現地調達にたよっている。持っていくものといえば、個人用テント・寝袋・ナイフ・個人用シングルコンロ・小型ナベ・強めの酒・コメ数合・マカロニ数袋くらいのものである。しかしそれだけでも結構な大荷物なのだ。さらに満足に食材を持ってこれたら現地での食材調達に終始する必要はないのだが、それにはさらに大荷物になることを覚悟しなければならないし、第一そんなに何でも持っていったら家にいるのと変わらないではないか、という考えがあって、あえて何も持っていかないのである。
しかし今回の神島テント旅ではその考えが仇となった。海の食材を期待していたのだが、海は漁師すら船を出さないほどの大荒れで、新鮮な魚介類も手に入らない。あるのは島に数軒だけある雑貨屋の缶詰とかレトルト食材である。島の人々もまた、海の漁獲事情に大きく影響される生活をしているのだ。
海は大きいので、一度荒れたらそんなにすぐにはおさまらない。いつまでも高波を睨んでいても仕方がないので、おとなしく缶詰やらレトルトパックを買い込んでおいた。浜で米を焚いてレトルト食を食うと、もう本当にやることがなくなった。しかしそれが逆にわくわくして、本当に今日は何もしないぞっ!という心持ちになった。ダッチョもボーボも同じようで、ダッチョはテントのジッパーを全開にして海を見ながら寝袋にくるまっている覚悟を決め、ボーボは砂浜に寝ころがってAMラジオを聞きながらうたた寝をはじめた。俺はというと、浜にころがる漂着物をいろいろ眺め歩くという、3人の中ではいちばん有意義そうな行動に出た。

浜の漂着物というのは面白いもので、思いもつかない物がたくさん転がっている。たとえば洗濯用洗剤のボトル。飲料ペットボトルのポイ捨てはありがちだが、洗濯用洗剤のボトルのポイ捨てはそうそう目にすることがないのに、浜にはあちこちに転がっている。おもしろい。そしてなぜか靴もたくさん転がっている。それも数メートル離れて、必ず左右ペアで転がっている。次に多いのが、魚釣り用のウキだ。これは納得がいく。どこかの釣り師の釣り糸が切れて、ぷかぷかとこの浜にたどりついたのであろう。島の浜には必ずウキが転がっているので、いつも俺は島に行くときの釣り道具のなかでもウキだけは持ってこない。浜で拾ってそれを使えば済むのである。今回の旅では釣りはできそうにないが、いつもの習慣でそれを拾って歩いた。そうしているうちにもうずいぶんテントから離れ、遠くの磯まで来てしまっているが、磯というのはまた楽しいのだ。いろんな生物がいる。目立つのはイソギンチャクで、ふらふらと波にただよっているのを見ているだけで楽しい。カキなどの岩場につく貝類が見事にぜんぶ獲られているのはさすが海女漁の盛んな神島だなあと関心しつつ、転々と岩をとびすすむ。カメノテやマツバ貝はたくさん岩についていたが、手ぶらで来たので獲らずに、岩に座ってしばし白い波頭が砕けるのを眺めたりした。
もうこれ以上進めないというところまできて、テントのほうへ引き返すことにした。帰り道では流木を拾い集めながら歩く。これは夜に焚火をしながら酒を飲むためである。しかし流木はふつう、染みこんだ塩水が乾燥を促進してカラッカラに乾いているものなのだが、昨日の大雨の影響でかなり湿っており、ひとつひとつ重たい。この湿り具合では焚火をしても蒸気を含んだケムリがすごくてたまらないだろうな、と思いつつも仕方なくそんな流木をワキにかかえて帰っていった。
テントのある浜に帰ってくるとダッチョとボーボの姿がなかった。ポリタンクもなくなっていたので、二人でまた中学校に水をもらいに行ったようである。俺は磯で見たちいさな生物の話をしたくてワクワクしていたのだが、誰もいなくなったテント村の、テント布のパタパタはためく音をしずかに聴きながら、拾い集めた流木で焚火をすることにした。さして目的のない炎を眺めて焼酎をポケットからとりだし、小学生の頃から来たくてしょうがなかった神島にいま自分はまさにテントを張っているんだ、ということにひとり胸を弾ませながら、その割にしずかにシェラカップの焼酎をすすって空を仰いでいた。気持ちがいいったらしょうがない。まいったなぁ。
しばらくするとダッチョとボーボがポリタンクに真水をたっぷり汲んでテント村に戻ってきた。少しコーフンしている。話を聞くと、水を汲ませてもらった中学校の女教師となにやらウカレ話をしてきたようだ。キャッキャと騒ぐ二人を見て、コイツらのハイテンションにすっかり乗り遅れてしまったな、と、ちょっと磯の生き物にコーフンして遠出をしてしまった自分を悔やんだ。くそう、なんてうらやましいウカレぶりだ!
しかし浜にもどった俺たちは何もすることがない。いよいよ本格的にヒマが襲ってきて、ヒマでヒマでうわあぁぁぁぁぁぁぁぁ!!!!なんぞと天高く叫ぶほどになり、誰ともなく浜に打ち上げられた浮き玉を拾ってきてキャッチボールをはじめ、誰ともなく木の棒を拾ってきてバットとなり、野球が始まった。しかしながら、俺たち三人は昼間っからすでに酔っぱらっており、玉は打てず、ちょっとカスってフライとなった球もキャッチできず、ブザマに砂につまずいて顔から着地するようなヨレヨレっぷりであった。誰も来ないような奥まった浜にテントを張ってよかった、と、ぐらぐら空中に揺れる玉を追いかけつつ顔にじゃりじゃりと砂をまとわりつつ、ぐらぐら揺れる脳のなかで静かに思った。

さして何もなく過ぎた三日間は、1年経った今でも寸分の狂いもなく鮮明に目に焼きついているほど、憂鬱で、しかしとても忘れがたき思い出となっている。
あの神島のどうしようもない風が恋しくて、今でも俺は一人でいろんな島に出向いている。

神島から京都に帰って、あいかわらず慌しいバイトの毎日を送っているのだが、なんとなく島のゆっくりとした時間の感覚を引きずっていて、気がつけばボーっとしてしまっていることがよくある。
寝袋にくるまって嵐の音をききながら不思議と感じていた安堵、風にうなる山の木々、急な階段のつづく細い路地、集落ですれちがうオバさん、島のことをいろいろ教えてくれた神島中学校の先生たち、学校の赤土のグランド、海からドーンと切り立った崖、水平線から堂々と昇る朝日、朝日をうける神島灯台や監的哨、ヒビ割れた道路、下校する小学生の元気な挨拶、老人のために灯油運びを手伝う中学生たち、古びた生活雑貨屋のおじい、水道のない頃に活躍したであろう小さな溜め池、所在無く立ちつくす犬っころ、草むらで昼寝しているネコ、オババたちの井戸端会議の光景…。
毎日なにかと忙しくて本当はボーっとしている暇などないのだが、ときどき人目をぬすんでは一人になって風に吹かれてみたりして、神島の余韻を楽しんだりしていた。
時は流れ、退屈で貧しくてしかし楽しくてしょうがなかったハイツ新喜での男の共同生活も、俺の転勤を機に幕をおろし、俺はひとり大阪の片隅で生活をはじめた。
もう気付けば半年になるが、いまだにこの土地には馴染めていない。毎日仕事を終えて帰るマンションの部屋は、どこか自分の帰るべき場所だとは思えず、引っ越してからもいつまでも荷解きができずにいる。引越しで用意したダンボールを、半年経った今でもまだ全ては開けられていない。
そして、仕事の休みを見計らって出かける島では、気持ちの全てを開け放ってくつろいでいる自分がいて、とても嬉しい。